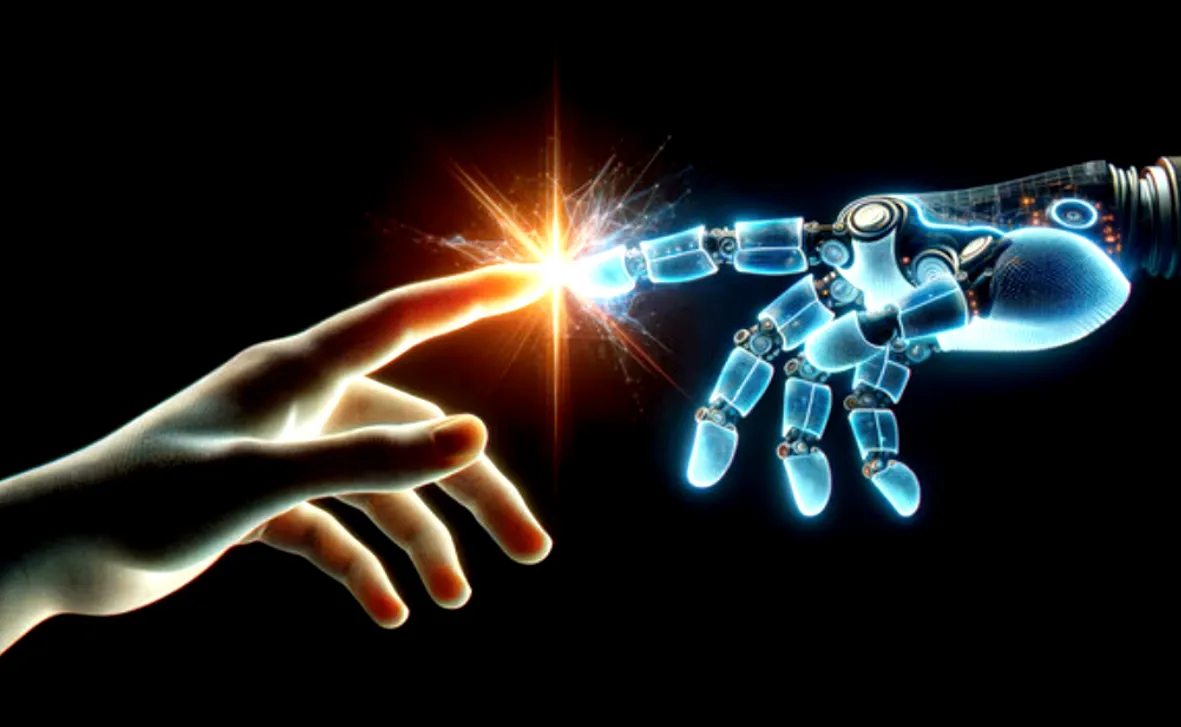- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース
ロボット活用の現場では、異なるメーカーのロボットを用途に応じて運用する場面も想定されます。
例えば物流倉庫では、荷物を運ぶロボット、在庫を管理するロボット、清掃を行うロボットなど、複数種類のロボットが同時に稼働するといった具合です。しかし、これらのロボットの制御システムはメーカーごとに異なるため、スムーズな連携が難しく、導入・運用コストの上昇を招いていました。また、ロボットと建物設備(エレベーターやセキュリティゲートなど)との連携も課題となっています。こうした状況を受け、ロボットの標準化への期待が高まっています。
製造現場から物流、サービス業まで、異なるメーカーのロボットを連携させ、効率的な運用を実現する「ロボットの標準化」。国際規格の整備が進む一方、日本独自の規格作りも進行中です。本記事では、グローバルとローカル、両面での標準化がもたらすビジネスチャンスと、企業が押さえるべきポイントを解説します。
標準化で広がる3つのビジネスチャンス

(引用元:大和ライフネクスト)
ロボットの標準化は、企業にとって大きなビジネスチャンスをもたらします。特に注目すべきは、異なるメーカー間での連携の実現、導入・運用コストの削減、新規参入の障壁低下という3つの側面です。それぞれの面で、具体的にどのような可能性が広がるのか見ていきましょう。
異なるメーカー間での連携の実現
ロボットの制御システムを標準化することで、異なるメーカーのロボットを効率的に連携させることが可能になります。具体的には、各ロボットの位置情報を一元管理し、狭い通路でのすれ違いや、エレベーター利用の順番待ちなどを最適化できるようになります。
例えば、配送ロボット、清掃ロボット、案内ロボットという異なる種類のロボットを同時に稼働させ、スムーズな連携を実現している実証実験の例もあります。このような連携が可能になると、限られたスペースでも多くのロボットを効率的に運用できるようになります。
導入・運用コストの削減
標準化された仕様に基づいてロボットを導入することで、システム連携のための追加開発コストを抑制できます。現在、多くの企業では異なるメーカーのロボットを導入する際、それぞれのシステムを個別に連携させるための開発が必要となっています。
しかし今後、標準化が進めば、そのような追加開発は不要になります。さらに運用面でも、異なるロボットを一元的に管理できることから、管理者の教育や日々の運用にかかるコストを大幅に削減できる可能性があります。
新規参入の障壁低下
標準化が進むことで、新規参入企業にとってもロボット開発がしやすくなります。標準規格に準拠した製品を開発することで、既存システムとの互換性が保証され、市場参入のハードルが下がることが期待されます。
実際に、物流支援ロボットや清掃ロボットの分野では、標準的なインターフェースを採用することで新興企業の参入が増加しています。このようにロボットの標準化は、産業全体の活性化にもつながっているのです。
企業が知っておくべき標準化の最新動向
ロボットの標準化は、国際レベルと国内レベルの両方で急速に進展しています。これらの動向を理解することは、今後のロボット導入や開発戦略を考える上で重要な要素となります。
国際規格の整備状況
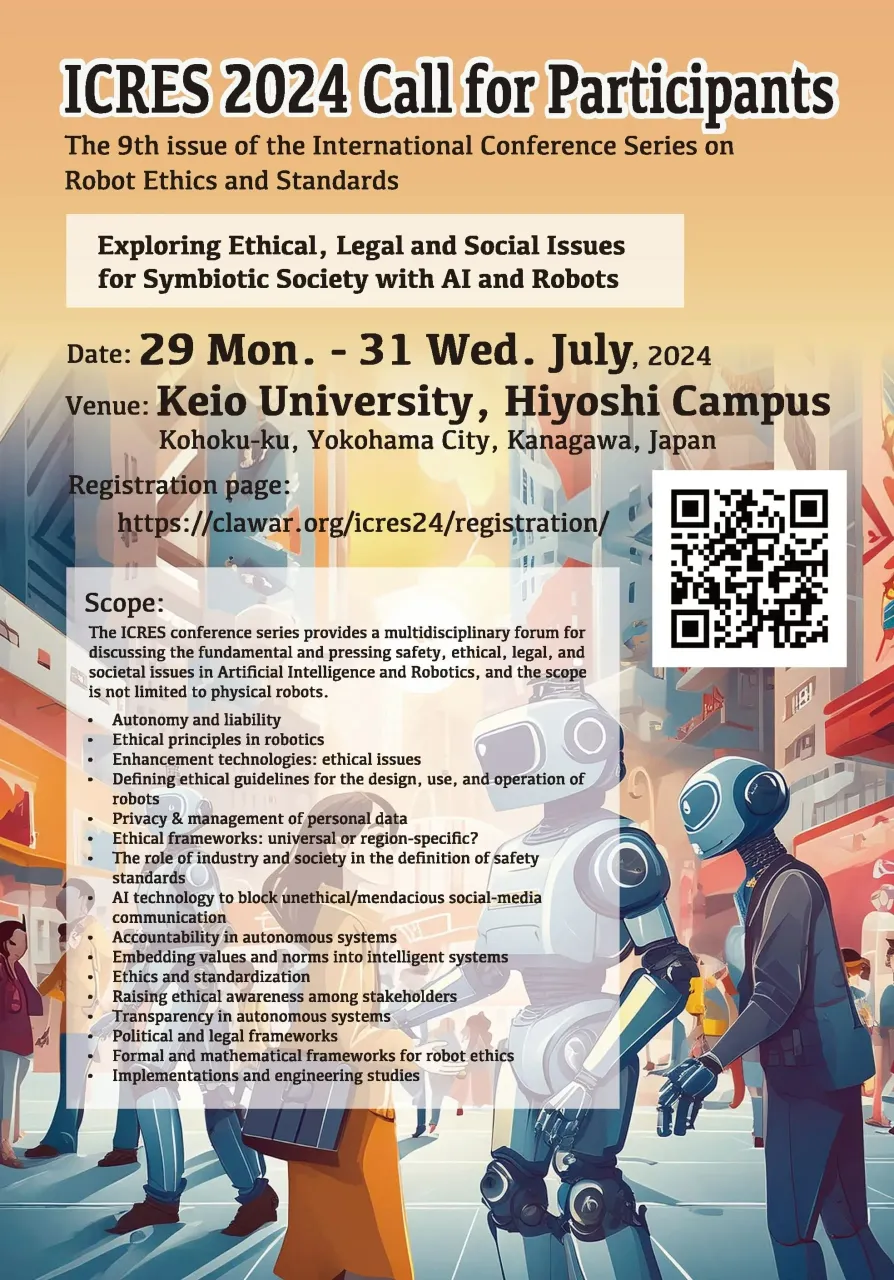
ロボットの倫理と標準に関する国際会議シリーズの第9回(ICRES 2024)が開催された(引用元:ICRES 2024)
経済産業省は欧州連合(EU)と協力し、ロボットの国際標準化を目指した取り組みを進めています。特に注目されているのが、ロボットと建物設備の通信連携に関する規格化です。欧州には世界有数のロボットメーカーが集積しており、それら企業との協力関係を通じて、日本もグローバルなロボット市場の発展に貢献することが期待されています。
日本発の標準化への取り組み

(引用元:NECネッツエスアイ)
国内では、大手システムインテグレーターをはじめとする企業が、複数のロボットを群管理するための標準規格案を策定しています。この規格案は、実際のオフィスビルでの実証実験を通じて有効性が確認されており、国内の標準規格としての確立を目指しています。さらにこの取り組みは、将来的に国際規格への提案も視野に入れており、日本発の技術標準として世界展開される可能性も秘めています。
標準化時代のロボット導入戦略
企業がロボットを導入する際は、現在の標準化動向を踏まえた戦略的な選定が重要です。国際規格への対応状況や、他社製ロボットとの連携実績、そして建物設備との連携可否など、さまざまな観点からの検討が必要となります。また、将来的な規格対応の可能性やインターフェースの拡張性、さらにはメーカーの標準化への取り組み姿勢なども、重要な判断基準となるでしょう。
これからのロボットビジネスに求められること
ロボットの標準化は、単なる技術的な規格統一にとどまらず、新たなビジネス機会を生み出す可能性を秘めています。国内外で進む標準化の動きを注視しつつ、自社のビジネスにどう活かせるか、積極的な検討が求められます。
特に、複数のロボットを連携させた新しいサービスの創出や、標準化されたプラットフォームを活用した効率的な運用など、さまざまな可能性が広がっています。ロボットビジネスの未来を見据え、標準化という追い風をどう活かしていくかが、企業の競争力を左右する重要な要素となるでしょう。