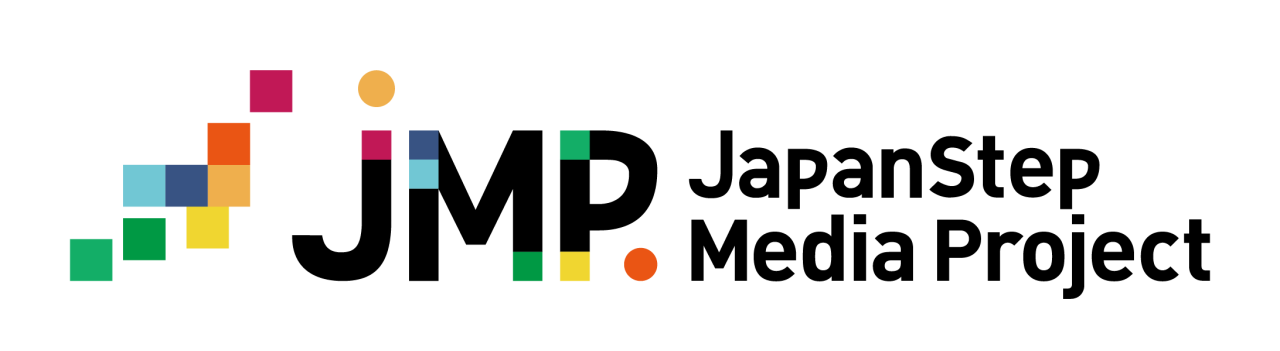- 総合TOP
- 宇宙
- AI
- ロボット
- WEB3・メタバース
ワクワクした気持ちで映画を観る瞬間や、子どもと笑顔で楽しむテーマパークの演出。そうした感情を揺さぶる体験を、ロボットビジネスに転用できるとしたらどうだろうか。日本のロボット技術は世界トップクラスだが、その社会実装を阻んでいる要因の一つに「見た目」という壁がある。
「日本のロボットは、正直デザインで損をしている部分がある。人はまず外見で惹かれるものだ」。そう語るのは、40年にわたり映画やCM、テーマパークの造形を手がけてきた株式会社ビッグワンの岡部 淳也さん。同社が立ち上げたロボット外装専門スタジオ「ロボカバー」が手掛けるのは、単なる装飾ではなく「選ばれる理由」を設計する試みである。エンターテインメントで培われた造形の知が、ロボット産業に何をもたらすのか。その可能性を探る。(文=JMPプロデューサー 長谷川 浩和)
お話を聞いたのは…

株式会社ビッグワン
岡部 淳也 さん
1965年生まれ、神奈川県横浜市出身。10代後半から特撮・造形の世界に入り、映画、テレビ、CM、アニメ、アミューズメント施設などエンターテインメント領域で幅広く活躍。プロデューサー、ディレクター、脚本家、ビジュアルスーパーバイザー、特殊造形ディレクターとして、企画から造形・VFXまで一貫して手がける。1989年に特撮スタジオを設立後、円谷プロダクションの副社長・クリエイティブ統括も歴任。現在は株式会社ビッグワンにて、映像制作で培った知見をロボット外装など新領域へと展開している。
40年のエンタメ造形がロボットに接続した理由
ロボットが工場の奥から人の生活圏へと進出し、その評価軸は静かに変化しつつある。処理能力や稼働率といった数値化しやすい指標だけでは、もはや導入の決め手にならない。人と同じ空間で稼働する以上、「どう見えるか」「どう受け取られるか」という感覚的な要素が重要になっている。
この変化を、誰よりも直感的に捉えていたのが、株式会社ビッグワンの岡部 淳也さんである。映画、CM、テーマパークといったエンターテインメント分野で40年以上にわたり造形を手がけてきた岡部さんにとって、「人の心を一瞬で掴む」という命題は、仕事の前提条件だった。
岡部さんは19歳で造形の世界に入り、20代前半から大型映像作品や話題作に携わってきた。造形とは単なる装飾ではない。カメラワーク、照明、役者の動き、観客の視線。そのすべてを前提に成立する「機能する美」である。動くこと、壊れないこと、演出に耐えること。その積み重ねが、結果として「リアリティ」と「説得力」を生み出してきた。
そうしたキャリアの延長線上で生まれたのが、ロボット外装専門スタジオ「ロボカバー」だ。一見すると異分野への挑戦に映るが、岡部さん自身は「やっていることは同じだ」と語る。「ロボットも、動く前提の存在。そこに人が感情を重ねる以上、見た目は決定的に重要になる」(岡部さん)。

同社が手掛けたプレゼンロボ。「カッコいい」ことも重要な要素だ
日本のロボット産業は、技術力では世界トップクラスにある。一方で、社会実装のフェーズにおいて「感情設計」が重視され始めている。安全性、耐久性、コストで優れているのはもちろん、人と向き合うロボットにおいて、「第一印象」は単なる装飾ではなく、機能の一部になりつつある。
ロボカバーは、そうした認識の転換点に立つ取り組みだ。エンターテインメントで培われた造形の思想を、実用ロボットへと翻訳する。その背景には、「これまでの経験を、次の世代の産業に接続したい」という岡部さんの思いがある。
 プロジェクト受託や共同開発など、事業の相談も増えているという
プロジェクト受託や共同開発など、事業の相談も増えているという
人の目に触れる時代、ロボットに問われる第一印象
ロボット市場はいま、大きな転換点にある。かつての主戦場は工場や倉庫といった、いわば裏方の現場だった。工作機器や産業用ロボットは、性能と安定稼働こそが評価軸であり、人の視線を強く意識する必要はなかった。しかし現在、ロボットは清掃、搬送、受付、警備、案内といった領域へと急速に広がり、日常的に人の目に触れる存在になりつつある。
 同社が外装制作した空港案内ロボ「mini MORK」。私たちの生活にロボットが確実に浸透してきている
同社が外装制作した空港案内ロボ「mini MORK」。私たちの生活にロボットが確実に浸透してきている
この変化に伴い、導入現場で重視されるポイントも変わりつつある。機能差が縮まり、一定水準を満たすロボットが市場に出揃うなかで、選定の決め手となるのはスペック表に書かれた数値だけではない。岡部さんが指摘するのは、次の三つの要素である。
第一に挙げられるのが、「安心感・親しみやすさ」だ。人と同じ空間で稼働するロボットにおいて、第一印象は想像以上に重要な意味を持つ。カッコいい、カワイイといった感覚的な評価は、単なる嗜好の問題ではない。利用者や通行人が無意識のうちに抱く心理的ハードルを下げ、「受け入れられる存在」になるための前提条件である。

 プレゼンロボでは外装から内部メカまでを制作した
プレゼンロボでは外装から内部メカまでを制作した
第二は、「空間・ブランドとの調和」である。ロボットは単体で存在するわけではない。商業施設、オフィス、公共空間など、それぞれに固有の世界観やブランド文脈がある。その中に設置されるロボットが、施設のトーンや企業のメッセージと噛み合っているかどうかは、導入効果を大きく左右する。ロボットが浮いて見えるのか、それとも自然に溶け込むのか。その差は、外装設計によって決まる部分が大きい。
 3メートルの大型ロボット「パトレイバー」ではデータ設計・FRP造形を手掛けた
3メートルの大型ロボット「パトレイバー」ではデータ設計・FRP造形を手掛けた
第三が、「機能美の実現」である。見た目を整えることが、機能を犠牲にしては意味がない。可動域を妨げないこと、メンテナンス性を損なわないこと、安全性を確保すること。その前提を満たしたうえで、動くことでさらに魅力が引き立つ外装が求められる。ここで言う美しさとは、装飾性ではなく、機能と一体化した美しさである。
岡部さんが強調するのは、これら三つの要素を最初に伝える役割を担うのが「外装」だという点だ。中身の性能がいかに優れていても、まず人が接するのは外見である。そこで感覚的に受け入れられるかどうかが、その後の評価や活用に大きく影響する。
ロボカバーが目指しているのは、単に外側をデザインすることではない。用途や設置環境、さらには企業や施設が描くブランド戦略、展示計画までを踏まえたうえで、ロボットの「立ち位置」を設計することにある。ロボットを「機能性の存在」にとどめるのではなく、「選ばれる存在」へと引き上げる。そのための外装を、戦略的に構築していくという考え方だ。
人の目に触れるロボットが増えるほど、こうした視点の重要性は高まっていく。外装は、単なる後工程ではない。ロボットが社会に受け入れられるための入口であり、ビジネスの成否を左右する重要な設計要素なのである。
量産にも対応。エンタメ業界で培った技術が光る
では、その「外装」という重要な役割を、どのように具体的な価値として実装していくのか。ロボカバーの特徴は、外装を単独のデザイン工程として切り出すのではなく、設計・素材・量産という一連のプロセスを通じて成立させている点にある。思想を語るだけで終わらせず、現場で使われるかたちにまで落とし込む。その実装力こそが、同社の強みだ。
ここで浮かび上がるのが、40年以上にわたって培われてきた造形ノウハウだ。映画やテーマパークの現場では、造形物は「止まっていて美しい」だけでは不十分だ。役者や機構と連動し、繰り返しの動作に耐え、観る角度や距離が変わっても世界観を崩さないことが求められる。こうした条件下で磨かれてきたのが、動くことを前提とした造形設計である。
この経験は、ロボット外装と極めて相性が良い。ロボットもまた、可動域や重量バランス、安全性といった制約の中で設計される存在だからだ。見た目の印象を整えながら、動作や運用を妨げない。その両立を成立させるためには、外装を「被せる」のではなく、構造の一部として理解する視点が欠かせない。ロボカバーが得意とするのは、まさにその領域である。

本物さながらの迫力。こうしたトーキング恐竜も企画・デザインからシステム設計、外装、内部メカ制作まで一貫して手掛けてきた
素材選定と表現手法の幅広さも特徴的だ。ロボット外装というと、硬質な樹脂素材を想像しがちだが、それが唯一の正解ではない。用途や設置環境によっては、柔らかさや温かみを感じさせる質感が求められる場面も多い。ロボカバーでは、シリコンや繊維といった素材を含め、目的に応じた選択肢を持っている。
特に繊維素材を用いた外装は、人の目に触れるロボットにおいて有効な選択肢となる。関節の動きを妨げにくく、視覚的にも心理的にもハードルを下げる効果がある。触感や見た目の柔らかさは、数値化しづらいが、確実に受け手の印象を左右する要素だ。外装を通じてロボットの「キャラクター」を設計するという発想は、こうした素材の選択によって具体化されていく。
 ホールガーメント®によるロボット専用「繊維外装」を用いた柔軟で親しみやすいロボット外装ウェアを研究開発・テスト制作中だという
ホールガーメント®によるロボット専用「繊維外装」を用いた柔軟で親しみやすいロボット外装ウェアを研究開発・テスト制作中だという
現場では、試作で終わらせない量産対応力も評価されているという。外装デザインは、コンセプト段階では評価されやすいが、量産や運用フェーズに入った途端に現実とのギャップが露呈することが少なくない。コスト、耐久性、製造ばらつき、保守性。そのいずれかが欠ければ、ビジネスとして成立しない。
ロボカバーは、プロトタイプ制作にとどまらず、量産を前提とした設計や製造体制まで視野に入れている。既存の製造ネットワークを活用しながら、外装を「作品」ではなく「製品」として成立させる。この視点があるからこそ、展示用や実証実験用に終わらない外装設計が可能になる。
 オートバイ3分の1レプリカ (3Dデータ・複合3Dプリント・仕上げ制作)は精密模型の事例のひとつだ
オートバイ3分の1レプリカ (3Dデータ・複合3Dプリント・仕上げ制作)は精密模型の事例のひとつだ
さらに特徴的なのが、既存ロボットに対するカスタマイズ対応だ。新規開発だけでなく、すでに市場に出ているロボットに対して、用途やブランドに合わせた外装の再設計を行う。色や質感の変更にとどまらず、企業や施設が伝えたいメッセージを反映させることで、ロボットの役割そのものを再定義することができる。
ここで重要なのは、ロボカバーが外装を「見た目を良くするための付加価値」として扱っていない点である。外装は、ロボットと人、ロボットと空間、ロボットとブランドをつなぐインターフェースだ。その設計次第で、ロボットが果たす役割や評価は大きく変わる。
ロボットが人の目に触れる存在になるほど、第一印象の重要性は増していく。その第一印象を、感覚論ではなく設計として扱う。そのための技術と経験を持っていることが、ロボカバーの本質的な価値と言えるだろう。ロボットが社会に定着していく次のフェーズにおいて、外装という領域が確実に競争軸の一つになっていきそうだ。
取材を終えて
岡部さんがこれまで携わってきた仕事の中には、日本を代表するものが数多くあり、実際に私自身もワクワクしながら触れてきた体験がありました。そうした記憶と結びつく造形を生み出してきた方が、いまロボット業界に向き合っている。その事実だけでも、胸が熱くなり、可能性も感じました。
取材中はロボットの話にとどまらず、映画やものづくりの話など、私が脱線させてしましたが(笑)、振り返ると、岡部さんが語った一つひとつが「人の心を動かすとは何か」という問いに通じていたように思います。技術や機能の話だけでは語れない部分にこそ、ロボットが社会に受け入れられていくためのヒントがある。そのことを、対話を通じて実感しました。
ロボットそのものを理解し、自らつくり、同時に人を楽しませる現場にも長く携わってきたからこそ、見た目と機能性を切り離さずに語れる。その言葉には、経験に裏打ちされた説得力があります。エンターテインメントで培われた造形の力は、ロボットという実用領域で何を変えていくのか。ロボットが人の目に触れる存在であり続ける限り、その問いはこれからも重要であり続けるはずです。岡部さん、お話の延長戦は是非飲みながら聞かせてください(笑)。